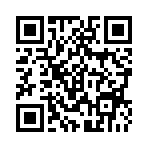グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年09月03日
畑にも炭!!
 イシコー 石井です。
イシコー 石井です。最近、食品の安全性の問題が重要視されています。
農薬や化学肥料は、病虫害を防いだり、収穫を上げるために有効ですが、使い方を誤れば、地力を奪い、環境を破壊し、何より人の健康を害する結果となってしまいます。減農薬、減化学肥料の農作物づくりの方向へ農業は向かっています。
農薬や化学肥料を使用せず地力を回復させ本来の土での農業を可能にする農業資材が炭です。炭は無数のミクロの孔が集積した構造体となっており、この構造が土壌に散布した場合に養分や水分を保持する力や植物の生育に有用な微生物を繁殖させるための空間となり、土壌の通気性・保水性・透水性などの作用の他、保肥力が向上するのです。土壌環境が良くなると、作物が丈夫に育ち、病虫害への抵抗力も増すので、農薬や化学肥料の使用量を減らすことができます。
Posted by 社長係り at
16:01
│Comments(0)
2014年09月02日
炭入りの壁
 イシコー 石井です。
イシコー 石井です。本日は室内の調湿・消臭の話です。部屋の湿度は気候やライフスタイルに応じ変化します。湿度が高すぎても低すぎても快適ではありません。室内の湿度を調整するのに、現在の一般的な住宅はその構造上、エアコンや除湿器、加湿器等に頼らざるを得ない状況です。しかし、このような機械に頼るのではなく、より自然に湿度の調整を行えれば身体にも環境にも理想的と言えます。エアコンや除湿器などなかった頃は、湿度の調整は漆喰や木炭、本物の木材などが調湿材料として使われてきました。これらは湿潤な日本の気候に最適な建築素材です。写真は顆粒状木炭が混ぜてある漆喰の壁です。
Posted by 社長係り at
11:55
│Comments(0)
2014年09月01日
炭の調湿効果!
イシコー 石井です。
今回は炭を住宅の床下に使用する目的についてです。
調湿効果が目的です。日本のような長い梅雨の時期と高温多湿な時期のある場所では、湿気による床下の耐久性を保つ対策が必要です。床下の湿気は、木材や断熱材が吸着し、押入れや床下部分など目につきにくいところで結露します。カビが発生しやすくなり、カビをエサにする微生物が住み着き、シロアリなどの被害がでやすくなります。
家の耐久性だけを考え、シロアリ消毒や薬品処理をしなければ耐久性のない木材を使うために、シロアリ駆除剤や木材の防腐剤に含まれる薬品で体の不調を訴える人がいます。薬品の影響は少なからず受けています。微量な薬剤が一日一日少しずつ溜まるのが一番怖いのです。家の耐久性はもちろん大切ですが住む人の健康を一番に考えるべきではないでしょうか。
床下に炭を敷くと、木材や断熱材が吸着していた湿気は炭が吸着して、乾期には放出する作用を繰り返し、木材の含水率を低下させるので、半永久的にカビ・シロアリの住みにくい環境にします。炭を敷き込む量が少ないと、炭が飽和状態になり、効果を発揮できなくなります。出来れば燃料用の木炭ではなく住宅の床下調湿を目的に造られた製品を使用して下さい。特にアレルギーやシックハウス対策として炭を使用する場合は注意する必要があります。
今回は炭を住宅の床下に使用する目的についてです。
調湿効果が目的です。日本のような長い梅雨の時期と高温多湿な時期のある場所では、湿気による床下の耐久性を保つ対策が必要です。床下の湿気は、木材や断熱材が吸着し、押入れや床下部分など目につきにくいところで結露します。カビが発生しやすくなり、カビをエサにする微生物が住み着き、シロアリなどの被害がでやすくなります。
家の耐久性だけを考え、シロアリ消毒や薬品処理をしなければ耐久性のない木材を使うために、シロアリ駆除剤や木材の防腐剤に含まれる薬品で体の不調を訴える人がいます。薬品の影響は少なからず受けています。微量な薬剤が一日一日少しずつ溜まるのが一番怖いのです。家の耐久性はもちろん大切ですが住む人の健康を一番に考えるべきではないでしょうか。
床下に炭を敷くと、木材や断熱材が吸着していた湿気は炭が吸着して、乾期には放出する作用を繰り返し、木材の含水率を低下させるので、半永久的にカビ・シロアリの住みにくい環境にします。炭を敷き込む量が少ないと、炭が飽和状態になり、効果を発揮できなくなります。出来れば燃料用の木炭ではなく住宅の床下調湿を目的に造られた製品を使用して下さい。特にアレルギーやシックハウス対策として炭を使用する場合は注意する必要があります。

Posted by 社長係り at
15:34
│Comments(0)